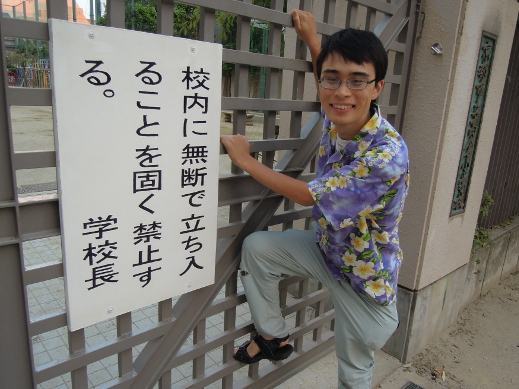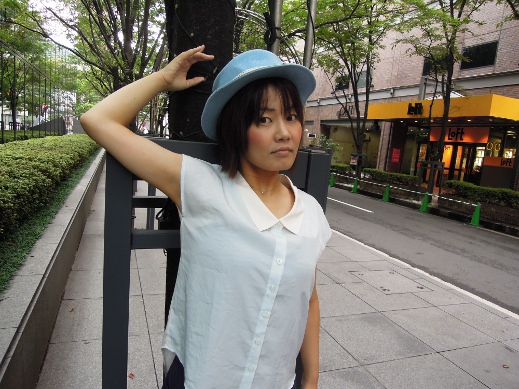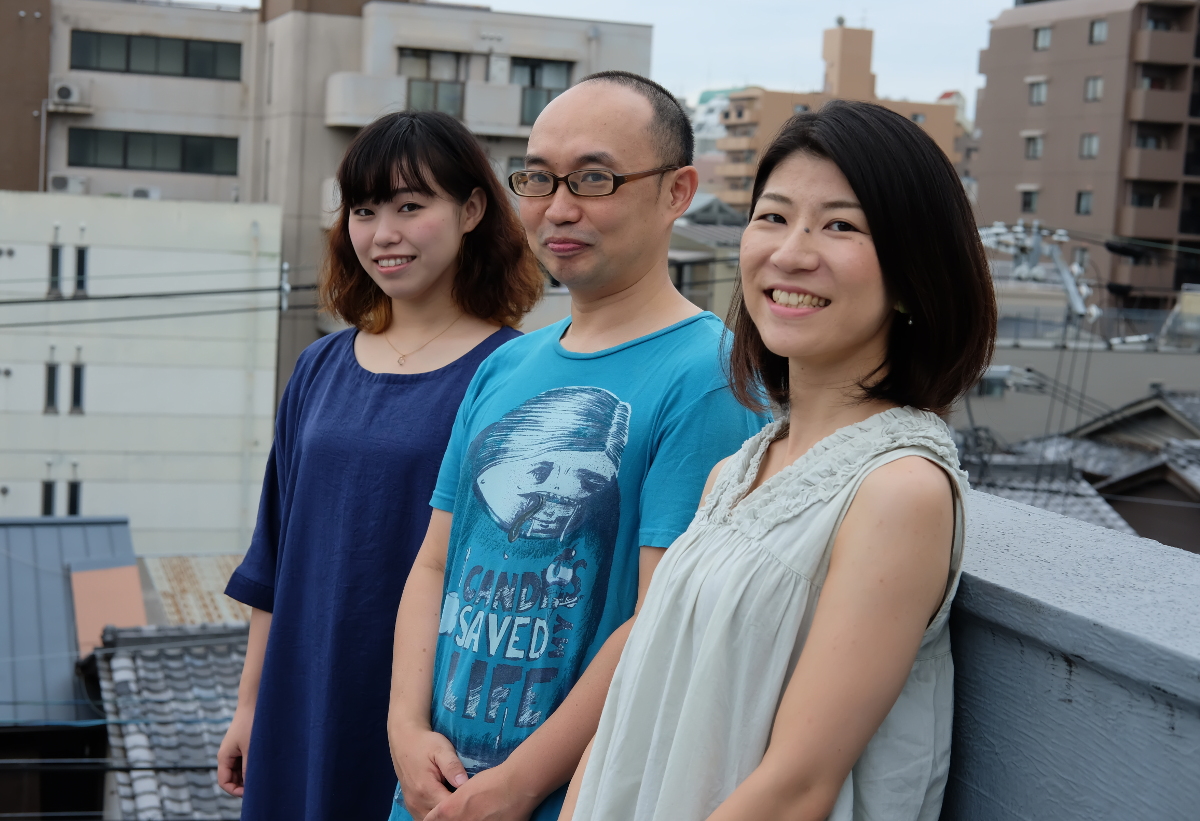最近
- __
- 今日はよるべの田宮ヨシノリさんにお話しを伺います。どうぞよろしくお願いいたします。最近田宮さんはどんな感じですか?
- 田宮
- よろしくお願いします。どんな感じというのは、どうですかね。最近はうさぎの喘ギの公演に俳優として参加するんですが、その稽古でバタバタしてます。
- __
- 「メメントモリを忘れるな」ですね。見に参ります。
- 田宮
- ありがとうございます!それと並行して、次のよるべの公演の台本を書いてる感じですね。書きながら俳優やって、みたいな感じです。
よるべ
関西小劇場で俳優として活動する田宮ヨシノリが2022年に立ち上げた演劇ユニット。作・演出を田宮が担当し、京都を拠点に活動している。会話劇を中心に、人間が持て余しがちな「どうしようもなさ」に着目し創作を行う。旗揚げ公演『深呼吸』(2022年12月、於:ウイングフィールド)にてWINGCUP2022 優秀賞受賞。
うさぎの喘ギ第11回公演「メメントモリを忘れるな」
公演期間:2025/5/16~19。会場:イロリムラ・プチホール。出演者:アンドヨ美穂 田宮ヨシノリ 保井岳太 作・演出:泉宗良 制作・主催 うさぎの喘ギ
よるべ「くじらのいびき」

- __
- よるべの前回公演「くじらのいびき」、非常に面白く拝見しました。まずはそのお話から伺えればと思います。ある事件がキッカケで会社に行けなくなって引きこもっている女1の部屋に訪れる旧友や同僚たちの会話というあらすじでしたが、会話がハイスピードで抑揚も削ぎ落されているのに全くストレスなく台詞が聞けるという、これまでにない観劇体験でした。田宮さんご自身にとってはどんな経験でしたでしょうか。
- 田宮
- 僕は俳優歴の方が長くて、よるべという団体自体、2022年くらいに立ち上げたばかりでまだ3年もやったかやってないかくらいで。「くじらのいびき」は3回目の公演として、それまでの公演のフィードバック、反省をちゃんと活かせたかなと思います。お客さんこそ少なかったですが評判は結構良くて、自分がやりたかったこともできたし、けっこう満足でした。
- __
- 女1を演じられた香川由依さんに取材した際、稽古では「セリフの間を詰める演出方法」をされておられたとのことでした。その演技指導がどういう効果をもたらしたのか?思うに、会話って突き詰めると「反応の繰り返し」ではないかと。反応を役者、ひいては人間が完全にコントロールするのってものすごく難しい。だから会話の土台には、反応・反射というアンコントローラブルな層が横たわっている。つまり「間を詰める」というのは、そういう管理しきれない反応・反射をあえて抑えて、役柄の個性を際立たせる手法なのではないかと。
- 田宮
- 役柄の個性、役そのものが舞台上に立ち上がるようにというのは、確かに意識していました。自然な反応を抑えるということについては、その俳優の生きている世界、つまり実際の現実世界?における俳優にとっての自然な反応が、無意識的に起こらないようにコントロールするということに気をつけていました。つまりそれは、アンコントローラブル、コントロール不可なものを無くすという意識ではなく、むしろ、無意識的な、俳優の生理で生じてしまう「間」をコントロール可能にしていくということを念頭においていました。
- __
- その発想は、どうやって生まれたのでしょうか。
- 田宮
- 実はウイングカップに参加した旗揚げ公演「深呼吸」のときには会話がちょっとダラダラした演技、俳優の現実世界における自然体に近い演技でお願いしてたんですよ。僕が俳優出身だから、「俳優がやりやすいようにしたほうがいいっしょ」って思ってたんですけど、公演後、万博設計の橋本さんに「俳優の生理でやらせすぎだよ」って言われて。「俳優はその場に居たがるけど、役が居たがるかどうかは考えないと」って。最初は全く意味がわかんなかったんですよ。でも、去年、樋口ミユさんのPlant Mの公演「WWW」に出たときに、間を詰めたり、喋ってる時は動かないとか、厳密なルールを守って演技する経験をして、「ああ、こういうことか」と。俳優の生理で動くと「俳優」になってしまうけど、劇世界のスピードや時間に合わせるそのルールに従うことにより劇世界の「役」になるんだなーとなんとなく思いまして。そうした方法論をよるべの稽古場に持っていったらどうなるかしら、ということを試しました。
- __
- なるほど。
- 田宮
- Plant Mに参加する前の2回目の公演「きろについて」では、とりあえずスピード上げたり、声を大きくしたりってやってみたけど、いま考えると俳優の生理じゃないところの劇世界のルールみたいなことを感じていたのかもしれなかったですが、突き詰められていなかったんです。今回は、稽古の最初の方に俳優の生理を徹底的に無くしていって、例えば「セリフを喋っている間は動かない」「次のセリフは間を詰めて即反応」みたいなルールをとりあえず設定していました。それをシーンごとに細かく調整して、ルールとして俳優と共有した感じです。相手のセリフ終わりに間を置かずに喋り始めるには、相手のセリフが終わるまでに次の喋り出しの身体を作らないといけない。というような。でもそれを1シーンずつ、1台詞ずつに適用するのは物凄い労力なので、方法論を作り、ルールを定義しました。それがどういう効果を生んだかというと、俳優の生理を無くすことで役の内面が出てくるんじゃないかって思ったんです。人間の反応って完全には消せないから、ルールで縛った先に残るものが、役の反応と一致するんじゃないかと。これは個性を削ってるように見えますが、僕は全然違うことをしていると思ってます。ルールさえ守れば、立ち位置とか声の大きさとかは自由で良いし、ルールを守るためにこれまで無意識だったことを俳優がコントロールできるようになるという。それが逆に俳優のグルーヴ感や役の生き生きした感じを引き出すんじゃないかと思いました。もしかしたら、出演者の皆様は最初「意味わかんない!」って思ったかもしれないですけど。
よるべ「くじらのいびき」
脚本・演出: 田宮ヨシノリ 期間:24/9/13~16 会場:The side 出演:宇垣サグ、香川由依、久野泰輝(REFUGIA)、山西由乃(Gesu◎・劇団ケッペキ)、山本魚
方法と、広がる闇

- __
- その方法論が、「くじらのいびき」の世界観や照明プランとめっちゃハマってましたよね。
- 田宮
- 本当ですか?嬉しいです。
- __
- ニートの部屋やまさに暗い海の底。閉じた空間なのにどこまでも広がっていくブラックボックスで、来訪者がその世界に試される話だと勝手に思っています。まるで、息継ぎが出来ない海底で喋っているかのように映じました。
- 田宮
- この手法って、どの劇にも応用できると思っていますが、今回は特にテーマとマッチしたのかもしれません。俳優がルールを理解して動いてくれていたから、劇世界とルールがちゃんと噛み合いましたし、女1をお願いした香川さんは中でも特にルールを厳守してくださっていたので、女の部屋のルールに巻きこまれていくみたいなのが、作品と響き合ったのかも。
- __
- その女1が、泣いたり叫んだりするシーン、めっちゃ良かったです。
- 田宮
- あのシーン、僕も好きなんですよ。稽古も本番でも「叫べそうやったら、叫んでもろたらっす。叫ばなくてもいい可能性もあるんで、息だけでもいいかもっす」って香川さんに任せてたんで、回によって全然違いました。叫ばない回もあれば、呼吸だけで終わる回も。
- __
- 私が観た回は叫んでました。あのシーンは、女1が「変わる兆し」を見せる瞬間だったのではと思います。
- 田宮
- 最初に脚本を書いたときには、女1が衰弱していくイメージだったんです。冷蔵庫の物がなくなったり、スイカも食べられなかったり。でも、俳優の演技を見ながら、「あ、ちょっと救われる感じもあるな」って感じて。書きながらも、俳優に任せた部分が大きかったです。
- __
- 俳優の力が際立ってましたね。親友の死や二股だとか、世界から切り離されたような経験。そこから外に出なくなったのだろうか。
- 田宮
- 努力クラブの少し前の公演で「どこにも行きたくないしここにもいたくない」っていうタイトルの公演があって、合田団地さんって天才だと思ってるんですけど、このタイトル知らなかったらこのタイトルつけたかったなって思ってて。でもつけれないんで、そこからもう一歩踏み込むには、「どこかに行きたいしここにもいたい」にしないとあかんのかなって漠然と思ってて。一般的な価値観?である外に出るのが正しいっていう前提をひっくり返して、「ここにいたい」って願望、寝てたらなんか勝手にどこかいけてたらいいな、みたいな。
- __
- その小さな世界で戦ってる感じがしました。
- 田宮
- 戦ってましたよね。叫びって、そういう戦いの結果なんじゃないですかね。
「きづけば」

- __
- 先日のCTT京都での「きづけば」も大変面白かったです。お母さんが観客に話しかけるシーン、幽霊なのか遺影だったのか、仕掛けと戯曲がハマってましたね。「きづけば」は、家族の面映ゆさに焦点を当てた作品だと思っています。そこに向き合って光をあてた。
- 田宮
- 僕の言葉だと「ちょっとした気まずさ」みたいなものを意識しました。特に兄弟の関係性とか、出演者のお二人と話し合いながら作っていきましたね。
- __
- 分かりますよ。
- 田宮
- ですよね。弟が優秀で、兄貴は実家から出られず、母は弟にデレてるけど、兄との関係はどうなんだろう、みたいな。血が繋がってるから喋らざるを得ないからこその気まずさ。昔は仲悪かったのに家を出て社会性身につけて急にいい奴になったりとか。家族ってそんな感じですよね。
- __
- そういうことだと思います。「きづけば」は四十九日法要というウェットで同時にドライな社交空間の中で、そういう気まずさと、反面にある愛みたいなものが際立っていました。演出をされている中で特に記憶に残ったことは?
- 田宮
- 「くじらのいびき」とは真逆のアプローチを試したんです。CTTって実験的なことをやる企画だと思っていたので、ずっとやってみたかった「ゆっくり動く・喋る」をテーマにしました。元々は、コロナ禍の時に、学生演劇の演出をちょぴっとしてまして、コロナの影響でZoom稽古なんかをせざるを得ず。稽古だっていってんのに、間がどうしてもできてしまうから、間を詰めるのはやってられないからあえて一文字一文字ゆっくり喋ってみようぜとなって。その当時は太田省吾さんの「プロセス」っていう演劇論集を読んでた影響もあって。
- __
- ゆっくり喋る?
- 田宮
- セリフを一文字ずつゆっくり。すると早く喋るのと違って、言葉を完全に理解してないと喋れないんですよ。それが面白くて。「きづけば」は、昔に書いた15分の戯曲を30分にするために、ゆっくり喋る手法を取り入れたんです。
- __
- なるほど・・・
- 田宮
- それが面白かったんですね。セリフが文字列じゃなくて、表現そのものにならざるを得ない感覚があり。つまり俳優って結構適当に喋ろうと思えば喋れるし雰囲気で喋れるんですけど、それができなくなる。また、感情的には早く喋りたくなるけど、ゆっくり喋ることで、俳優の感情と役のギャップが見えて、面白い瞬間が生まれることもありました。
- __
- セリフを極めてゆっくり喋ると軌道修正が難しくなるという現象もありそうですね。途中でニュアンスを変えたくても、それまでのニュアンスが観客に届いちゃってるから、調整がきっと大変ですよね。また、単語のニュアンスの完全性を守るために音のアレンジがとても難しくなる。
- 田宮
- 逆に、時間があるからコントロールしやすい面もあるんですよ。野球の難しさわからんすけど、変化球投げる時に160キロじゃなくてスローボール投げるみたいな?早く喋ると流れでごまかせちゃうけど、ゆっくりだと一語一語に思考の波形が乗るんです。今後、早いセリフにこの分解能をどう活かすことができるのか、7月の公演では試行の余地があるかもしれません。
C.T.T.京都 vol.124
公演期間:2025/3/21~22。会場:左京東部いきいき市民活動センター。よるべ『きづけば』作・演出:田宮ヨシノリ 出演:久野泰輝(REFUGIA)、山本魚、田宮ヨシノリ/あたらよ『ういしぃ。』作演出:鴨梨 出演:岩越信之介(劇団なべあらし)、橘、立脇魁人、西村霞
解釈
- 田宮
- 外部のワークショップに行って何かを経験しても、結局自分のところではやらないことが多いんですけど、CTTは「現代演劇訓練」の訳だということもあったので、せっかくだから今回は騙されたと思って色々やってみようと思いました。たとえば、昔に書いた戯曲だということもあり、戯曲の解釈に稽古期間の大部分を当てたり。
- __
- そうなんですね。
- 田宮
- ちょうどこの稽古前に鳥取県の鳥の劇場という劇団の演劇塾に参加したり、稽古期間に三重県の第七劇場の演出家の鳴海さんのワークショップを受けたりしてて。その時に、戯曲の文学的解釈について経験しました。これまであんまり聞かなかったし、ちゃんとやったことなくて、戯曲の解釈をみんなでやるって。多分、作家を兼任しない演出家だけの団体とかではやってるんじゃないかと思いますけど、正直まだ勉強中なんで、よく分からないですね。
- __
- 小劇場レベルだと、「ここにたどり着いてください」みたいなオーダーだけが出されることが多いですかね?
- 田宮
- そうですね・・・どの現場でも俳優はそこまで行く努力を自分の責任でしないといけないとは思いますが、前提に全員で解釈を行ったということがあるのとないのではだいぶ違うのかなとも思います。
- __
- 個人だけのパフォーマンスでは限界がありますね。
- 田宮
- まさにそう思います。全員一丸となって解釈して作り上げたものには、個人プレーは敵わないかもしれないですよね。もし、自分が海外の難解な戯曲を扱うカンパニーにいたら、ひとりじゃ何もできないと思います。全員でアタックさせていただかないと。比較的普段の生活に近い戯曲を扱っていると、「簡単に答えにはたどり着けない」という葛藤をあまりせずにやっていけちゃうところがあると思うんです。だから今回の企画では普段の生活に近いような戯曲でもちゃんと戯曲解釈をやってみようと試みたのですが、まず俳優それぞれで解釈が全然違ったんです。なので、どう筋を立てていくか、統一していくのかとかは苦労しましたが、それが意外と面白かったですね。
- __
- その過程そのものが価値であり、経験もまた価値ですね。
- 田宮
- この間、Plant Mのリーディング公演「げきじょうのひ #0 序と云い切れズ」にも出演したんですけど、稽古では俳優が8人いて、それぞれの役、自分の役も他の人の役も、1回ずつ読むだけだったんです。何の指示もなく。ただ読むだけ。でもそれで、8回読んで、一周し終わったあとには劇世界のことがすごく分かったんです。演劇って、一役を生きるってだけじゃ、世界の一部しか見えてない。でも本当は劇世界全体があって、そのなかで自分の役をどう生きるかを決定するっていう状態が理想的だと思いました。「この役をどう演じよう」ではなく「戯曲の世界」がある。
- __
- 理解を三次元的に埋めていくってことですね。抜け漏れが出るのは当然だけど、ジョハリの窓を広げて三次元に近づけていって、意味を時空間に満たす作業なのかも。観客はその情報立方体の中を旅する。
- 田宮
- まあ、この考え方がいいかどうかは分からないですけど、何もないよりはずっといいと思うんです。お客さんがどんな経験をするのかは分からない。でも、方法論として持っておくことは大きいですね。ただ、俳優として舞台上で演じるときには全部捨てるんですよね。しかし核となるエッセンスだけは俳優の身体に残っている。これが観客と共有されていくんじゃないですかね。
- __
- エッセンスが残っている。
- 田宮
- そうですね・・・舞台上で生きるために俳優はたくさん考えて、それを全部捨てる。でもエッセンスが体に残っていて、観客はそれを頼りに劇を旅していく。ガイド役として、照明や音響が補っていくこともあると思います。
- __
- 演劇はやっぱり全員で共有する部分が大事なんですね。
- 田宮
- ある演出家の方に、「演劇に間違いはないっていうけど、間違いはあるんだよ」っていうようなことを言われたことがあって。ある種の正解を探すためには、それこそ演劇には正解はないかもしれないけど、それを探すためにはやってはいけないこと、「間違い」を探すことは重要だと思っていて。なので、自分達が手掛ける大筋や根底は全員で共有しておかないとダメなんだと思います。そうじゃないと「間違い」が分からないのかなとか。
- __
- それを見極めるためにも共通認識が必要なんですね。
- 田宮
- 大筋を全員が持っていれば、何が劇世界じゃないことなのかが分かると思うんです。最初に話してたような「劇世界をどう作るか」ってことと矛盾しないためにも、そのエッセンス?根底を全員が共有しておくといいのかなとか考えたりしています。
質問 藤村弘二さんから田宮ヨシノリさんへ
- __
- 前回インタビューさせていただいた藤村弘二さんから質問をいただいてきてます。「役者をやる時、演出者の経験が生きたなとか、良かったと思うことはありますか?」
- 田宮
- 僕、俳優を先に始めてるんです。その時は多分すごい演出家目線で考えてたというか、「この役にはこういう役割があるから、こういう風にした方がいいだろう」みたいな考え方だったんですよね。
- __
- なるほど。
- 田宮
- でも最近ようやく、演出家目線から離れて。もっと俳優本位というか・・・「俺はこう今思ってるんですよ」みたいな、「僕はこういう気持ちなんですよ」とか、「役はこういう気持ちになってたんやな」とか思うようになってきて、それから「ここでこう行きたいっすよ」みたいな感じになってきたんです。第三者視点からの制御性みたいなものから。うまく言えないんですけど、もうちょっと心の仕事というか、自分の心をどうコントロールするか、いやコントロールじゃないな、どう感じているかを、どう外に出すかっていう俳優的な頭に最近すごくなってきて。だから聞かれてるのはそういうことかな。演出家すぎたなって思って、反省してるんですよ。なんかちょっと外から見過ぎてるというか。もっとこう、うちにうちに入らないといけないなって。
- __
- 俳優を始めた時は演出家目線、それが今は視線が役者本位になってきたと。
- 田宮
- まあそれはきっと、演出家としての経験があるからこそなんでしょうね。解釈とかやる上では結局やってることって一緒なんで。第一にその劇の世界をどう生きるか、どう生きているのか、みたいな方に最近はすごい注力しているという感じですかね。答えになってますかね?
- __
- 大丈夫だと思います!ありがとうございます。
三角形の片隅は

- __
- 7月公演の意気込みを伺えればと思います。どんな作品になりそうでしょうか?
- 田宮
- どこまで話していいのか分からないんですけど・・・これまで、舞台のモデルみたいなものは特に考えずに書いてたんですけど、今回はウィングカップで優秀賞を取ったので、協力公演ができて、それを使ってウイングフィールドで公演をやろうと思っていて。ウイングフィールドという劇場には俳優としても思い入れがすごくあるので、やるなら「ここでやる意味」みたいなものをちゃんと考えたいなって思ったんですよ。アメリカ村って行ったことあります?
- __
- ありますよ、一応。
- 田宮
- 僕、関西出身じゃなくて。少し前に初めてアメリカ村に行ったんですよ。独特な雰囲気ありますよね、あそこ。でも、誰もここを演劇にしてないなって思って。
- __
- 確かに、あまり演劇の題材になっている印象はないですね。
- 田宮
- だから、「アメリカ村を舞台にしてみよう」と思って。まあ、本当にただ舞台にしただけなんですけど。そこにいる人たちの雰囲気から着想を得たというぐらいです。
- __
- 私も行ったの2回ぐらいですけど、古着が売ってる店の多いエリアですよね? 三角公園を中心に。
- 田宮
- そうそう。古着とかスケボーとか、若者カルチャーがちょっと下北沢っぽいというか、でもやっぱりそれとも違う独特な感じがあって。ライブハウスや飲食店も多いですし。僕が行った時、やたらと外国人が多くて。特に三角公園周辺には。もちろん日本人がいないわけではないんでしょうけど。で、その時ふと思ったんです、「三角公園にいたはずの人たちって、どこに行ったんだろう?」って。そんなエリアにいる人たちをモデルにして書いてみようかなって思って、今、頑張って書いてます。
- __
- ニート女性の部屋、四十九日法要、次は三角公園ですね。
- 田宮
- 舞台自体は、三角公園からちょっと離れたマンションの下の路地みたいな場所なんですけどね。
- __
- あ、だから三角形なんですね。
- 田宮
- そうなんですよ(笑)。どうしようかなって思ってます。あんまり「モデルにしました」って言い過ぎるのも良くないかなと思ってて、実際そこまで中身に関係ない気もしてきたし・・・僕、関西の人じゃないし、大阪弁でも書いてないし・・・どう見せていくか考えてます。さっき話していた方法論を、この作品でも試せたらいいなと思ってます。
よるべ「三角形の片隅は」
公演期間:2025/7/18~21。会場:ウィングフィールド。脚本・演出家:田宮ヨシノリ 出演:あっぱれ北村(シイナナ)、久野泰輝(REFUGIA)、熊谷帆夏(劇団アンゴラ・ステーキ)、田口翼(チーム濁流)、中村彩乃(安住の地/劇団飛び道具)、増田知就(ブルーエゴナク)、山本魚
これから
- __
- 今後のよるべはどんな感じで。
- 田宮
- シンプルな会話劇を大事にしていきたいです。あと、今は、社会問題みたいな大きなテーマより、個人のどうでもいい問題を丁寧に掘り下げていけたらなと。公演頻度は1年に1回か2年に1回くらいになるかもしれないけど、出来るだけやめずに続けます。
NORITAKEのトートバッグ(PAN)

- __
- 今日はお話伺えたお礼に、プレゼントを持ってまいりました。
- 田宮
- え、プレゼント。めっちゃ嬉しい!開けていいですか?
- __
- どうぞ。
- 田宮
- ひとからのプレゼントなんて2、3年ぶりですよ(開ける)めっちゃ可愛い。こういう横に広いバッグってあんまりないんですよね。縦長のトートばっかりで。
- __
- お買い物とかで使ってくださいね。
- 田宮
- 絶対使います。おしゃれで実用的。ありがとうございます。