好き放題

- __
- 今日はどうぞ、よろしくお願いします。筒井さんは最近、いかがでしょうか?
- 筒井
- おかげさまで、忙しくさせてもらっています。まあ順風万帆でもないという感じかな。
- __
- 私は逆境に立たされているというのが結構好きなんですけど、筒井さんはいかがですか。
- 筒井
- そうですね、そもそも演劇を選んでいる時点で、この現代社会においては逆境なんですけれども、もっと具体的には、なかなか自分がやりたいことを認めてもらえなかったり、賞をもらってから数年経って、昔ほどやりたい放題ではなくなっていたりして。それは僕のせいでもあるんですけど。
- __
- 好き放題出来なくなっている?
- 筒井
- 昔はお金の事なんか全く気にしないで作品を作っていたんです。すごい借金して公演を打ってたりしてました。それだけじゃ難しくなると思って方向転換をしていきました。やりきった感と共に辞めるのならともかく、お金の融通が効かなくなって、どうしようもなくなって辞めるのは避けたいです。
- __
- なるほど。
- 筒井
- ただ、やれる範囲でものを作るという事が習慣化されていくという弊害にも直面していて。発想力が上演空間に収まっていて、それを破るようなキテレツなアイデアが生まれにくくあるんじゃないかというのが、自分が生んでいる逆境といえるのかも。悩んでいるという訳じゃないんだけど。いまは活動の継続性を確保しつつ、発想力が劇場に収まらないようにするやり方を模索しています。
dracom
1992年、dracomの前身となる劇団ドラマティック・カンパニーが、大阪芸術大学の学生を中心に旗揚げ。基本的には年に1回の本公演(=「祭典」)と、同集団内の別ユニットによる小公演を不定期に行う。年に一回行われる本公演では、テキスト・演技・照明・音響・美術など、舞台芸術が持っているさまざまな要素をバランスよく融合させて、濃密な空間を表出する。多くの観客に「実験的」と言われているが、我々としては我々が生きている世界の中にすでに存在し、浮遊する可能性を見落とさずに拾い上げるという作業を続けているだけである。世界中のあらゆる民族がお祭りの中で行う伝統的なパフォーマンスは、日常の衣食住の営みへの感謝や治療としてのお清め、さらには彼らの死生観を表現していることが多い。我々の表現は後に伝統として残すことは考えていないが、現在の我々がおかれている世界観をあらゆる角度からとらえ、それをユーモラスに表現しているという意味で、これを「祭典」と銘打っている。(公式サイトより)
「しちゃう」
- __
- 実は私、dracomの祭典・公演はもれうた 、事件母 、弱法師 、この間のたんじょうかいしか拝見出来ていなくて。どれもとても面白かったんですが、やっぱりもれうたの衝撃は凄かったんですよ。
- 筒井
- ありがとうございます。
- __
- dracomの特徴といえば俳優の身体と台詞のズレだと多くの人が思い浮かべると思うんです。つまり、俳優の台詞を前に録音しておいて、本番時にはスピーカーでそれを流し、意図的にズレを作りだす事で、観客の受容器官は別々に俳優の演技を受け止める事になる。私はあれがとても好きでして。そうした演出を発想されたのはどのような経緯があったのでしょうか。
- 筒井
- 2007年に作品を作るという事で、企画書を書く事になって。その当時、ミュージカルに興味があったんです。好きとは言えないんですが、興味があって。
- __
- 興味。
- 筒井
- もれうたの前の2年間に2本、ミュージカル作品の祭典を作っていたんです。歌って踊って、でも歌はとてもへんてこりんなメロディで、アレンジもスカスカで。でも、いずれは静かなミュージカルを作れるようになりたいと思っていました。演劇計画2007参加に向けて企画書に書いたタイトルは「もれうた」で、公園で鼻歌を歌っている人、それだけで作品を作れないだろうかと思っていました。
- __
- わかります。面白そうですね。
- 筒井
- でも、格式高い作品にしちゃおうと。(この「しちゃう」という言い方をよくするんです)その格式高さがおかしみになるんじゃないかと思うんです。鼻歌で歌われているのはオペラの歌曲で、歌詞が映像で出てきて、鼻歌を歌っている人がいて、それだけの作品。でもそれだけの作品だったら多くのお客さんは寝てしまうだろうと思って。だからセリフのテキストを書きました。が、すると客の意識はそちらの方にばかり向いてしまう。僕は鼻歌の方にフューチャーしたかったから、どうしようと思って。だから、会話のセリフを録音して、それをちっちゃいボリュームで流せば鼻歌の方が勝つ。そのコンセプトまでは稽古場に持っていくまでに出来たんです。練習して、俳優が身体だけで演じられるようになった。
- __
- なるほど。
- 筒井
- しかし、それだと俳優がセリフを覚えない手抜きという事になってないか。努力の跡が見えないといけないという言い方をする人もいるんですよ。僕はそういう評価の仕方は好きじゃないんですけど、でもまぁ、努力の跡を示すために、俳優たちがセリフを覚えている事を示すために思いついたのが、事前に録音しておいて、俳優が身体だけで演技した後に遅れてセリフが聞こえてくるという演出をしたんです。これなら、俳優はちゃんとセリフを覚えていると示せる・・・そういうつまらない発想からだったんです。まあ、それを実際試してみたら、過去に体験した事のない感覚があったんです。これは面白いなと。
dracom 祭典2007 『 もれうた 』
公演時期:2007/9/8〜9(京都)、2007/9/29〜30(伊丹)。会場:京都芸術センター(京都)、AI・HALL(伊丹)。
dracom 祭典2010 『事件母(JIKEN ? BO)』
公演時期:2010/10/14〜17(京都)、2010/11/18〜21(東京)。会場:京都芸術センター(京都)、THEATER GREEN BOX in BOX THEATER(東京)。
dracom 祭典2012 『弱法師』
公演時期:2012/9/7〜9。会場:京都芸術センター。
音楽と、演劇と、身体と、

- __
- 興味があるやり方に「しちゃう」のが筒井さんの演劇なんですね。そこで伺いたいのですが、筒井さんが発見されたセリフと身体の時間的な分離は、革命的な手法として演劇史の延長線上に位置しているのでしょうか。それとも、人間存在なるものを、意図的に発生させたズレから問い直す意義に立脚しているのでしょうか。
- 筒井
- 後者ですね。確かにそれは後者なんですよ。最近になってようやく、自分がやっているのは演劇だと思えるようになりました。dracomが舞台芸術集団と名乗っているのもそこからです。舞台で何か、面白い事をしたいという気持ちは当初からあるんですが、それが演劇である必要はないなあと。そういう中で、例の実験が大きかったんです。ちなみに僕は音楽が趣味なんですが、劇中で音楽が鳴る時、「音楽が鳴ってるからここは盛り上げたいんだ」という見え方がするともう最悪なんですよ。そういうものが世の中に多い中で、演劇を後押ししたりとか、足をひっぱりあうみたいな関係じゃなくて。音楽と、演劇と、身体と、セリフというものが有機的に関わる表現を模索していたんです。その中で、ずらすという手法が、今までにない形で捕まえる事が出来たと思ったんです。演劇に革命を起こそうとかは考えてなかったですね。音楽好きだったから辿り着いたかもしれません。もしこのやり方を、演劇だけを志向する人が気付いたとしたらどうだったんだろう?それを深めたり継続したり、上演に持っていったとはちょっと思えないですね。
- __
- 音楽と空間と演劇。それらが同じ時間と場所に結実するものを、コンセプトから引き出せないかと考えているのですね。
- 筒井
- まあ、偶然に助けられたものかもしれないし、それを稽古場で初めて見た時面白がったのは僕だけだったんですけど。あの瞬間は、それまで目指していたものを掴んだと同時に今後の自分の方向性を広げてくれました。ただ、その広がりは用意されている劇場空間に集中してしまい、以降、それほど変な公演はしていないですね。もちろん、試みを面白いと多くの方に仰って頂いたし、僕自身も面白いと思っていたんですがその次へと越える為の何かを生むのに苦しんでいます。あの演出方法でどんどん作っていけばいいじゃないかという声もあるんです、が、実感としては「いくらでも作れそうだ」と思っています。テキストさえあれば。だから、いくらでも作れると思えてしまった時点で、これはブレーキを掛けないといけないと考えたんです。
純芸術
- __
- 私は小劇場を見る時に、納得出来なくても気にしないで見るという姿勢が身についていて。例えば言えてない俳優のセリフを無理矢理受け止めたり、間の不自然さに気持ち悪いと思ってもそこは目をつぶったりして、テンションを落とさずに見ているんです。そんな事を考えている時点で楽しんでいないのかもしれませんが。しかし、dracomを見る時は、そういう事はしなくていいんですよね、それはもう、上演する寸前に肌で感じるものがある。奇妙さが前提だったから?いや、それはもしかしたら、純芸術と呼べるようなものだからかもしれない。そう思います。
- 筒井
- うん。
- __
- 純芸術と呼べる演劇は、dracomの形をしているのかもしれない。それは、「良いコンセプト」があれば、それを味わえるだけで良い。そうした力強い作品をdracomで拝見出来るのはとても嬉しいです。
- 筒井
- そうした反応を貰えるのは嬉しいですね。
dracom Gala公演 ウイングフィールド提携公演 たんじょうかい
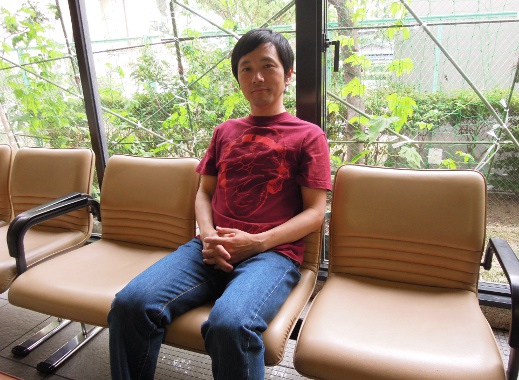
- 筒井
- 一般の人たちは演劇をどう捉えているんだろうと思って、Gala公演「たんじょうかい」という企画が生まれたんです。大勢の方に面白いと言ってもらえましたが、一方、dracomの祭典をいつも面白いと言ってくれるコアなお客さんは物足りないと。
- __
- dracomには珍しいストレートプレイでしたからね。
- 筒井
- 実はこの公演には狙いがあったんです。大阪のお客さんは、一体何に興味があって劇場に足を運ぶのか?という事です。戯曲か、俳優か、演出か?そういうリサーチの意味もあったんです、実は。上演後にお客さんに書いてもらったアンケートの結果と、公演後の声から総合したら面白い事が分かったんですよ。
- __
- というと。
- 筒井
- アンケートに「今日劇場に来た理由は何ですか?」という項目を設けたんです。僕は「見たことがない劇作家の作品を見てみたかった」が多いと思っていたんですね。その結果が出ていれば、お客さんは知らない劇作家の、過去の名作に興味がある。つまり、戯曲への興味が大きいという事になる。
- __
- そうですね。
- 筒井
- しかし、「dracomを観てみたかった」という答えが意外と多かったんです。みんな割と演出に興味があるという事が分かったんです。dracomを見に来る時点で少数派であることは否めないですけど。で、じゃあ、世に言われる大阪戯曲至上主義の正体とは?それは、ある作家の新作が、作家自身によって演出された戯曲に最も忠実な上演を見に劇場に来る事を指しているのかもしれません。であれば、お客さんが横に流れていかない。実際に「たんじょうかい」のアンケートでは、すでにある作家のファンの人で、未見の他の作家の作品を観てみたかった、という回答をした人はたった一人でしたから。戯曲至上主義というよりは作家個人至上主義と呼べるのかな。すると横の流れがより狭くなってしまって、広がりがなさそうな気がしてくるんだけれども。
- __
- 作家に人が付いていっているという事かもしれませんね。
- 筒井
- 作家という、保証なんですよ、きっと。演出が作家自身によるものが「本物」であって、その「本物」じゃない公演には足を運ばない、ということになっているのかもしれないですね。もっと多くの劇団や作家が「たんじょうかい」のように積極的に働きかけたらそれなりの成果が得られるのに。
dracom Gala公演 ウイングフィールド提携公演 たんじょうかい
公演時期:2013/6/22〜23。会場:ウイングフィールド。
質問 嵯峨 シモンさんから 筒井 潤さんへ
テント公演と、女三人
- __
- 筒井さんは今後、どんな感じで攻めていかれますか?
- 筒井
- 「たんじょうかい」のような地に足着いた演劇作品を作りつつ、僕が発見できた「ズレ」から広がった、従来にはない方法から模索していこうと思います。具体的な公演予定としては、秋にテント公演するんです。
- __
- テント公演!?
- 筒井
- 10人ぐらいが入れるテントで、いろんなところに持っていきたいなと思っています。
- __
- 面白そうですね!なぜテント・・・。
- 筒井
- ある条件下で作ってしまいがちな今の状況から抜け出したかったというのもありますし、実は昔から冗談で言ってたんですよ、テントでやりたいというのは。発想が劇場などのすでにある上演施設に収まりたくないという思いもあって。
- __
- 6月にはそよ風ペダル の公演もありますね。
- 筒井
- 高槻市のシニアの皆さんですね。劇場での公演ではありますが、素人ゆえに劇場に収まらない方々なんですよ。お互いに「客席に顔を向けていかな」とかって声を掛けあってくれるんです。シニアの方々だからこそ出来る、生の声に聞こえるようなセリフの言い方がどういうふうに受け止められるかですね。その辺りが楽しみです。
- __
- 「女3人集まるとこういうことになる」 は。
- 筒井
- 今稽古途中なんですけど、演劇をやっていてダンサブルになりすぎる瞬間と、ダンサーが演技になりすぎる瞬間の、本来ならダメ出しされてしまう、ダメな部分を集めるとこうなる、という事をちまちまと作っています。
高槻シニア劇団 そよ風ペダル 第1回本公演『モロモロウロウロ』
公演時期:2013/6/22・23。会場:高槻現代劇場 レセプションルーム。
DANCE FANFARE KYOTO参加『女3人集まるとこういうことになる』
公演時期:2013/7/6〜7。会場:元・立誠小学校 職員室。
MOLESKIN シャープペンシル(0.7mm)

- __
- 今日はですね、お話を伺えたお礼にプレゼントを持って参りました。どうぞ。
- 筒井
- えっ、そんなものがあるんですね。めちゃめちゃ嬉しい。(開ける)シャープペンシル?
- __
- 手帳用のものです。
- 筒井
- 入るかな。ちょっとはみ出るけど、今使ってるのがスカスカなので、ぴったりです。ホントに使います。







































