難問

- __
- 今日はどうぞよろしくお願いいたします。最近武田さんはどのようにお過ごしでしょうか。
- 武田
- よろしくお願いします。最近は次回公演の準備と、仕事で数学の研究をしていて忙しいです。
- __
- どのような研究をしているのでしょうか。あらましだけでも教えていただくことはできるでしょうか?
- 武田
- 保型形式論です。まず保型形式というものがあって、これは周期性を保つ関数なんです。しかも二重に周期性を保つ関数で、出てきた当初は整数とは関係なかったんですけど、いろんな保型関数を考えていくうちに、実は整数論とつながっていることが分かってきて、それを整数論的に扱おうっていうのが保型形式論です。これが一般的な理解ですね。そこから先も難しくなっていくんですが、何が分かるかっていうと・・・何が分かるんでしょうね。
- __
- それが他の学問に応用されたり、何か数学の別の分野につながったりすることもあるかもしれませんね。
- 武田
- その分野で一番大きい目標や難問とされているのが、リーマン予想ですね。リーマンゼータ関数というのも、保型形式に付随するL関数と呼ばれるものの一番シンプルな形で。リーマン予想で何が難しいというと「シンプルで、素朴すぎて、無味無臭すぎて手がつけられない」という点ですね。癖がまったくなくて逆に扱いにくい。それがリーマン予想を難しくしている理由です。
ユニットににふに
京都を拠点にする劇団「安住の地」派生ユニット。
「空っぽになったことなんてない」

- __
- 「空っぽになったことなんてない」、とても面白かったです。食べ物が完全に人工食になった世界――本当に“人工食”というか、生命を食べなくなったという世界観が示されている作品だったと思います。いろんな要素が詰まっていて、すごく考えがいがある作品だなと感じました。ご自身にとって、どんなご経験になりましたか?
- 武田
- もともとは5年前、20歳の時に書いた作品なんですが、その当時ぐらいから生き物を食べることに抵抗があって。
- __
- それがこの作品を描いたきっかけや動機と重なった部分もあったのでしょうか?
- 武田
- そうですね。なんだろうな・・・
- __
- 拝見していて、自分のことをすごく客観的に見ながら自分語りをしたいという感覚があったんですね。たとえば「この会話や発言はどのように評論されるんだろう」とか「どんな評価を受けるんだろう」とかみたいな視点が内在化しているような感じがあって、それがすごく面白かったです。
- 武田
- 他者の目をずっと意識している感覚。その感覚は私の元々の性分なんですけど、ほかの人はそんなに強くは認識していないのかな。他の京都界隈の演劇を観ると「本音をスパッと言う」タイプの演技が多い印象があるんです。でも私は「そんなに本心って簡単に言えないでしょ」って思ってしまう。自分でも本心なんて分からなかったりして、隠しながら、人にさらけ出せるところだけ細かくちぎって与えている――そんなやり方が自分の性に合ってるなと思います。
- __
- ありがとうございます。実は個人的に解釈に困るシーンもあって、この機会にぜひ伺いたく。風花(人造食をどうしても受け入れられず自然食を隠れて食べている人)が一人残された部屋で「黒ぼんた」(数年ぶりに再会した同級生である智英が部屋に持ち込んだ人造食。2Cm程度の黒い球形の食品)を頑張って食べて、誰が見ているわけでもないのに「美味しいじゃん」とつぶやくシーンが気になっています。実は全然美味しくなかったろうにわざわざ口に出す。誰も聞いてないのに。強がってるんでしょうね。でも、そうモノローグすることで何かが守られる、あるいは何かを壊そうとしている、どちらにしてもある意味、自壊的な意図が奥底にあると見て取れて非常に面白いと感じました。
- 武田
- 私もそうだと思います。
- __
- ちなみに黒ぼんたってどんな味がするんですか?
- 武田
- 黒ぼんた、どんな味なんでしょうね。私、実は味オンチなので、味についてはあまり深く考えてなかったんです。どちらかというと視覚的なイメージばかり意識していて。たまたまローソンにおいてあった商品で、私の思い描いていた黒ぼんたがおいてあって。ローソンプレミアムの小豆のお菓子かな。それを公演でも使いました。
ユニットににふに vol.00「空っぽになったことなんてない」
公演期間:2025年6月13日(金)〜15日(日) 会場:Alternative space yuge 原作:武田暢輝 / 川島愛音「唅」 作・演出:武田暢輝 出演 鴨梨 / 乱痴パック
距離

- __
- 「空っぽになったことなんてない」において、俳優にはどんなふうに作品に関わって欲しかったですか?
- 武田
- 難しい質問ですね。個人的に、役者が役とちょっと一歩引いた場所にいるのが好きなんです。でも、今回の二人とも、特に乱痴パックさんは「そうなっちゃった」と言ってたんですけど、いわゆる「役に飲まれる」状態、役に食われるような感じになってしまったそうで。
- __
- 役と役者の距離が近くなりすぎてしまった?
- 武田
- そうですね。それと、最初のほうでは私の思う感情とは真逆のトーンで演じていたシーンが結構多かったんです。そこが一番最初に躓いたところかもしれないですね。それを逆にして試してもらったりもしました。というのもあって、戯曲だけ読んだ印象と、実際に演劇として見た時の印象はかなり違うものになっている気がします。
- __
- 俳優がセリフのトーンをどう受け取ったか。
- 武田
- 普通はこうだろうというものとは結構逆だったので。
- __
- 全体的には落ち着いたトーンの会話劇に見えたと思いますけど、「女の子同士のポップなトーン」になると想像されてたり・・・?
- 武田
- もっと細かいところで、対等に話してる場面もありましたけど、私はむしろ「対等じゃない」ほうが良かったんです。通常の会話ではないコミュニケーションを経て再び会話に戻る――そんな関係性の組み立てがやりたかったというか。
- __
- たとえば。
- 武田
- 最初に風花の部屋に智英が来るシーン。見た目は対等に会話してるようだけど、実は智英が圧倒的に優位で、風花は完全に受け身ではじまるみたいな。
- __
- 智英は本当は「自然食」に憧れていて、それを抑えきれない自分を自覚しつつ、風花にはバレないように近づこうとする。でも無意識にマウントを取っちゃう――みたいな。
- 武田
- そのあたりが、私の作品の「味」かなと思っています。
- __
- 完全に恋愛とかは関係ないけれど、ドロドロした関係性、みたいな?
- 武田
- はい、そういう感情の混ざり合いが、すごく面白いなと感じています。
かわいそう

- __
- 命を食べなくなる、というテーマがとても奥深いと思いました。作中に登場する人造食って、“完全に命から切り離されたもの”という触れ込みで、たぶん科学的な化合物とかで出来ているんでしょうかどなど、それらももともと生物だったものからできてはいるんでしょうけどね。それはさておき人間が自然食ではなく“人造食”に切り替えて作中では3年ほど経った設定だと思います。登場人物全員、どこか余裕がなくなっているという印象を受けました。命を食べなくなると、人間は余裕がなくなってしまうものなのでしょうか。
- 武田
- もともと私はヴィーガンの人たちに関心があって。(私も)生き物を食べることに抵抗があったのは確かです。ただ、ヴィーガンの人は植物は食べる。そこは良いんだ、と。それは「切ってもまた生えてくるからいい」という言説もありますよね。でも、「切ってもまた生えてくるなら、例えばカニの足を食べてもまた生えてくるからいいんじゃないか」とか、そういう理屈も頭に浮かびます。ヴィーガンの方々も理性的に動物性のものを避けているわけですが、それでも大豆ミートなど、やっぱり肉に似たものを求めたりもしていて。理性と本能のせめぎ合いが、常にどこかで続いているんじゃないかと。結局、生き物を食べないというのも理性的な抑制の産物で、それを続けていると、どこかで本能的な爆発が起きるんじゃないか。
- __
- 食育って何なんでしょうね。
- 武田
- 難しいですよね。感謝して命をいただくこと自体には意味はあると思いますが、極論すれば豚や牛からしたら感謝されても知ったこっちゃないのかもしれませんし。その感謝の気持ちは、ある意味宗教というか信仰のようなもの、つまり人間が命を食べることへの理性的な嫌悪や葛藤を和らげるための儀式だと思ってるんですけど。
- __
- この世界の人たちがこれまでとこれからのことをどこまで考えているのか。作中ではそこまで大きくは描かれていませんでしたよね。世界観の設計は示されているけれど、どういう経緯でそうなったのかとか、世の中の大多数はどう思っているか、というよりは、この2人の関係や心情にフォーカスした構成だったように思います。
- 武田
- そうですね。
- __
- なので伺いたいのですが、ラストシーンで魚(風花の彼氏。魚。部屋の水槽に浮かんでおり、赤い魚体をしている。携帯電話を通して彼女と会話する)が智英に襲われてしまい食べられて・・・その直後、風花の口から発せられた「かわいそう」という一言に正直「それかよ」って驚きました。彼が食べられたのに・・・あの瞬間、風花は何か変身、変容したような印象でした。
- 武田
- 「かわいそう」という感情がすぐ湧いてくると私は思ってたんですけど・・・。
- __
- 彼氏が殺されて?
- 武田
- どう思われましたか?
- __
- 正直、ちょっとした怖さを感じていました。風花はもう人造食を口にしてしまい、人造食を疑う彼氏魚とのつながりが切れてしまっていたとはいえ、殺人者である智英を制止したり大声を出したりあるいは彼氏の遺骸を守ったりというようなアンコントローラブルな反応ではなく「かわいそう」というセリフが出てくる。その心の切り替わりの速さとか冷たさ・・・完全に魚を“消費”してしまったのではないか。どれだけ愛した存在でも、自分や相手が変わってしまえば、突然「映画のワンシーン」みたいに他人事になってしまう。その過程の早さ、切断感がとてもドラマチックで印象的でした。人が変わっていくこと、人と人の関係性が変わっていくことにも怖さがありますね。
- 武田
- 私自身、身近な親族が急に脳梗塞になってそのまま亡くなられた経験があって。生前元気だったときと、病院で寝たきりになってからとで、周囲の接し方が全然変わってしまうのを目の当たりにしました。お見舞いに来た人が「来たよ~」「どう。分かる~?」とか。物になったかのような喋り方で。そのことがすごく怖かったです。一方で、他者の死を迎える準備段階に入ると、どこかで心の中で切り分けや編集が始まるのかもしれない。「来たよ~」は自分のための言葉なのかもしれない。死を受け入れるために、受け入れる側が無意識に心の整理を進めていく――それが「かわいそう」という言葉に現れたと思います。
- __
- ありがとうございます。全然話はズレますが昔、関西ローカルのテレビで「おばあちゃんよかったね」という葬儀場のCMが流れていたんですけど、それを見たときぞわっとしました。
- 武田
- (少し笑う)
回路

- __
- 10月公演の「微睡みが黄色くなる前に」。統合失調症をテーマにされた作品ということですが、このテーマを選ばれたきっかけや動機について、何かお考えがあれば教えていただけますか?
- 武田
- これまでほとんど全ての作品で精神疾患や病気を題材にしてきたんです。たとえば一作目の「水の綻び」では吃音症の方が登場しますし、二作目では主人公が体が発光してしまう奇病を設定したり、他にも認知症、レビー小体型認知症を扱った作品もありました。今回は「現実」――つまり人間の認識の危うさというか現実の不安定さそのものに強く興味が湧いて。人が世界をどう見ているのか、世界は本当に安定しているのか?――そんな問いから、一般的な枠から“外れている”とされがちな人たちに興味があって。
- __
- なるほど。
- 武田
- 統合失調症は100人に1人はなると言われていて、決して遠い存在じゃない。学校なら3クラスに1人いるくらいの、本当に身近な存在です。
- __
- 私自身もとても関心があります。認知が現実と妄想の境界をどんどん曖昧にしてしまう。例えば、頭の中で渦巻く思考が、いつの間にか「他人が考えていることが自分の中に入ってくる」とか、「自分の自我の輪郭がにじんでしまう」、それ故に病識が持てない、今はごく簡単にそう理解しています。今回の作品制作にあたり、取材や文献調査などで印象に残ったことはありましたか?
- 武田
- 結構いろいろ調べましたが、統合失調症って本当に昔から知られているのに、実際のところ何がどうなっているのかはよく分かっていないんですよね。普通の妄想や空想とは明らかに違うけれど、その仕組みや感じ方について医学的にも解明されていません。ただ、最近ちょっと分かりだしてきたそうなんです。例えば幻聴の場合も、当事者の語りでは「声がする」とか「話している」とは言うけれど、「実際に聞こえている」とは言わなくて。「悪口を言うのが見える」「話してるのが見えた」とか、そういう独特な表現が多い。その理由はたぶん「それ以外の表現方法を持っていないから」で、そのまま語らざるを得ないのかな、と思っています。赤道直下の砂漠地域直下の人が「吹雪」という言葉を持たず、全部「砂嵐」で表現するしかない、みたいなものです。当事者になるしかその感覚を理解することは出来ないんですが、当事者もその感覚を表現する言葉を持っていない。
- __
- そうですね。
- 武田
- 最近統合失調症でわかってきたのは、「自分」というものが外に漏れる、外に出ていってしまうように感じる、という現象ですね。自分が他者になったような感覚がある。外の世界が変わってるのではなく、自分自身が変容してしまうことで、「自分が思った言葉が他者の声として聞こえる」――そんな状態です。内側にあるはずのものが、外に流れ出していく。こうした内と外のあいまいさ、不安や自己評価の低さが“他者に漏れ出している”ような感覚として表れる。ここ2~3年の研究で、やっとこういう感覚の輪郭が明らかになってきました。いわゆる「妄想」とは違うんですよ。
- __
- それこそ認識の病なんですね。
- 武田
- そうなんです。それから、自分の考えた言葉を「耳から聞こえる言葉」として捉える神経回路と、「自分が発した音」として捉える回路があって、それがうまく連動しないようなんです。だから「自分が喋った言葉が他人の声として聞こえる」みたいな症状が出るんですね。
- __
- 統合失調症のお薬ってありますよね。でもなぜ効くのかメカニズムが分からないことも多いそうですが。
- 武田
- ドーパミンの異常だとは分かっているんです。それを調整と症状が劇的に良くなることもあっても、なぜそれが「妄想」や「幻聴」とつながるのかは、まだ分かっていません。
ユニットににふに vol.01「微睡みが黄色くなる前に」
公演期間:2025年10月3日(金)〜5日(日) 会場:THEATRE E9 KYOTO 出演:沢栁優大 山下裕英(以上、安住の地) 伊藤泰三 鴨梨(あたらよ) 小山栄華(アナグマの脱却座) 橘 主催 安住の地 助成 京都芸術センター制作支援事業、京都府文化力チャレンジ補助事業 提携 THEATRE E9 KYOTO (一般社団法人アーツシード京都)
社会とあなた
- __
- 『微睡みが黄色くなる前に』。チラシ裏のあらすじを読ませていただいたのですが「久」(ひさし)という青年が主人公として登場するのかな?と思うんですが、彼の感情、たとえば怒りや悲しみを観る側はどのように捉えればいいでしょうか?もちろん彼に対して、共感や同情など、さまざまな気持ちも湧いてくる作品になるのかな、と想像しています。ただ、観る人によっては苦しい作品にもなるのでは・・・とも思いますが。
- 武田
- 私としてはそちらも大いに描きたいです。「当事者や周囲の人がただ苦しいだけの作品」にはしたくないです。どうにかしてある種の救いや出口、もしくはひとつの“解決の糸口”のようなものは提示したい。でも、もし本当にそれが簡単に見つけられたら、医療でもすでに解決されているはず…とも思ってしまって。やはり難しいテーマです。
- __
- 10月か・・・。公演楽しみです。公演に向けての意気込みをお聞かせいただけますか?
- 武田
- こうした疾患や疾病をテーマにされている作品の中でも、おそらく一番リサーチしている作品だと思います。相当数の論文を読み込んでいますし、当事者の声も収集して。身近な統合失調症の方の観察など、とにかくめちゃくちゃ調べました。
- __
- 素晴らしい。
- 武田
- 現代社会は「多様性」とは言いつつも、実際にはマイノリティの人々を排除する傾向があるのでは、と私は感じています。「自分は自分、あなたはあなた、それぞれ好きに生きてください」という世界観が広がっています。最近は不登校や引きこもりの生徒、子どもたちが増えていると聞きますが、それすらも「個性だから」「そういう人もいる」と簡単に受け入れられてしまう空気があります。でも、その方向に進み過ぎるのは、個人的には少し怖いなと思うんです。
- __
- 確かに。それは正義のように見えますしね。
- 武田
- たとえば、政治の話を出すのもなんですが・・・今の時代は「どの道を選んでも自由ですよ」と全てが開かれている分、「この道こそ正しい、みんなで一緒に歩もう」と強く旗を振って導いてくれる人や方針を待ち望む層も一定数いると思います。今回の選挙でも、そういう志向が強まっているのを感じました。だからもし強い国家主義が進んだとしても、案外「生きづらさ」は減る層があるのかも、とすら考えることもあります。
- __
- そうですね。
- 武田
- そういう人たちを社会がどう受け止めるかも大きなテーマで。どんな立場の人でも…たとえば私たちの身近にいながら、排除されがちな統合失調症のような疾患を持つ人たちも含めて、知らないと接することもできないと思うんです。
質問 きょん子。さんから武田暢輝さんへ
- __
- 前回インタビューさせていただいた方から質問をいただいています。きょん子。さんから質問です。「もし武田さんが私を使って何かを表現するなら、どんな手法でしてくださいますか?」彼女は自分自身がすごく美人であること、グラマラスな体型であることもよく理解しており「自分をどう使えば客受けするのか、パフォーマンスできるのか」といったことを常に意識しているそうです。その前提でどうぞ。ちなみに彼女は昨今の学生演劇の状況にもとても危機感を持っているとおっしゃっていて、「最近の学生演劇は基礎練をやっていないのは危険だ」とのことでした。また「学生のうちに恥ずかしいことも恋愛も留年も、キモいことは何でも済ませておいたほうがいい」と、「大学時代までに自分のやりたい事を済ませておけ」論を語っておられたのが印象的でした。
- 武田
- 私の興味だけになるかもしれないんですが・・・性愛や異常性癖と呼ばれる領域、それも小児性愛のようなきわどいテーマのどれかの表現。たとえば同性愛は病気扱いされないのに、なぜ小児性愛だけここまで社会から排除されるのか。社会システム上認められないのはもちろんだけど、どこまでを「治療の対象」と捉えるのか。すごくデリケートなテーマですが、社会的な抑圧と個人の欲望、理性と欲情がどうせめぎ合うのか。その微妙なニュアンスをパフォーマンスや表現に反映できる気がします。
- __
- きょん子。さんは理解力のある方なので、ディスカッションには付き合って下さると思います。
- 武田
- 「自己の魅力」を分かっていながら、それを活かして生きる人を演じるのが上手そう。
- __
- 彼女はその「他者認識」をとても強く把握されています。周囲からの認識を真摯に受け止められなければ出来ないことです。誠実かつ、繊細な心が基底にあるのでしょうね。小児性愛のような指向に相対したときどう反応されるかは未知数ですが・・・
- 武田
- 理性と欲望のゆらめきが僕は好きなので、そうした危険なバランス。きょん子。さんならその危うさをうまく表現できそうだと思いました。
UNCOLORED
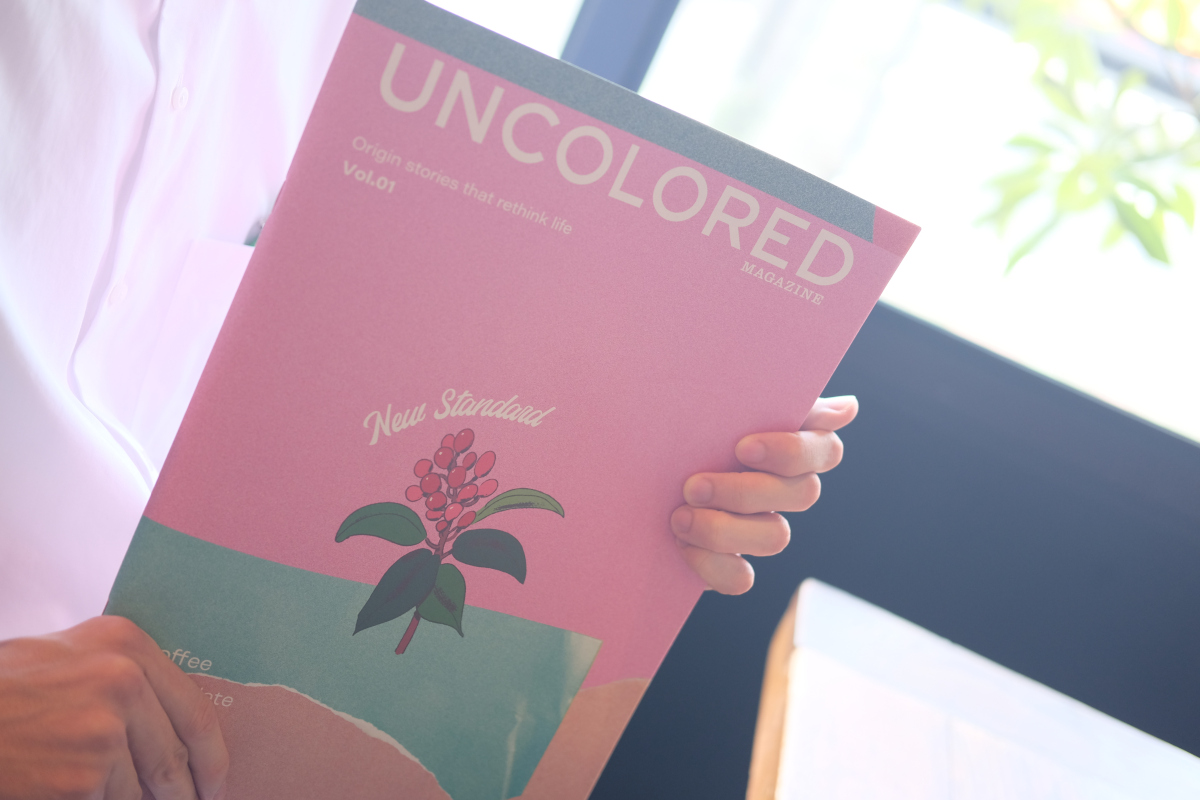
- __
- 今日はお話を伺えたお礼にプレゼントを持ってまいりました。
- 武田
- ありがとうございます。大きい。開けてみても大丈夫ですか?
- __
- ぜひ。
- 武田
- 失礼します。(開ける)
- __
- 新しく創刊された雑誌らしいです。今回はコーヒー特集の号です。ほかにも、いろんなスポーツやホテルを取り上げた雑誌のようです。リラックスタイムのおともになればうれしいです。
- 武田
- ありがとうございます。











