8月

- __
- 今日はどうぞよろしくお願いします。
- 田中
- よろしくお願いします。
- __
- 最近、田中陽太さんはどんな感じでお過ごしでしょうか?
- 田中
- そうですね。この前のENGEKI FRONT+の公演が終わりまして、また次の9月10月に大阪で本番の舞台があります。あとはワークショップのアシスタントだったり、演出助手だったり、ありがたいことに色々なお仕事で舞台に携わらせてもらっていて、忙しく過ごしている感じです。
- __
- ありがとうございます。演劇以外ではどうですか?
- 田中
- 演劇以外ですか。ちょうどお盆に入ったので、昨日も家族と旅行に行ったりしました。演劇面もそうでない面も、両立して楽しく過ごせています。
- __
- なるほど、それが一番ですね。ありがとうございます。
ベイビー、ラン
大阪芸術大学大学院 舞台領域所属の田中陽太が立ち上げた個人ユニット。団体名の由来は「赤ん坊のようにままならない身体と、それでも前に進みたい/走り続けたいと思う心」から。「ルール」に縛られた役者の身体性を通して、物語のコンセプトや登場人物の内面を浮き上がらせる表現を追求している。
ENGEKI FRONT+
公演期間:2025/6/28~29。会場:THEATRE E9 KYOTO。上演団体:劇団ゆうそーど。『せまいね、刹那!』 社会の居ヌ『立ツ鳥跡の天秤に鳴ク。然レド生きた空は在ル。』 ベイビー、ラン『君のからだは川になる』※追加販売分終了 灯座『あの日の忘れ物』
スモールシアターKIKIオープン記念 ロングラン公演企画 劇団アンゴラ・ステーキ×ベイビー、ラン 【 ABnormal Ceremony 】
公演期間:2025/9.21~10/5。会場:スモールシアターKIKI(大阪・千林)
「君のからだは川になる」の稽古場

- __
- ENGEKI FRONT+での演劇『君のからだは川になる』、大変面白かったです。死と生に向き合った作品ということで、構成がまとまりながらも挑戦的に尖っていたというか。シーンとシーンがザッピングされるような感覚があって非常に面白かったです。何より私が個人的に気に入ったのは冒頭のライブで、ミュージカルの一番盛り上がっている部分を冒頭に持ってきたという。「君のからだは川になる」は今回のための書き下ろしだったんですか?
- 田中
- はい、書き下ろしです。ただ、「死生について書こう」とか、何か明確なテーマを持って書き始めたわけでは実はないんです。これまで書いた作品や、全国学生演劇祭で削った台詞、書き途中のものなどを、コラージュみたいに自分なりに遊びながら作っていきました。そうするうちに最終的な方向性が見えてきて「今回は子供たちの話にしよう」と決まったのも、作り始めてしばらくしてからでした。最初はどんな物語になるかあまり見えないまま走り始めた作品でした。
- __
- それは、子供たちの話にした方が手応えがあったということでしょうか?
- 田中
- はい、そうです。自分で書きながら「これはどういう作品なんだろう」「どういう人物だったらこのセリフを言えるかな」と考えていたんです。その時に、親の帰りを待つ子供や、生まれてこられなかった子供たちの魂、みたいなイメージでセリフを言うと成立するかもしれない、と思いついて。最初は水の中の生き物など、全然違うイメージでセリフを喋っていたんですけどね。
- __
- 生まれなかった子供たちの話というのは、役者さんたちに稽古場で読んでもらったり、立ち稽古をしていく中で手応えを感じていった、という感じですか?
- 田中
- そうですね。漠然と「流れる」というキーワードは最初からあったんですが、それが途中から子供たちの物語になり、流産や生まれてこられなかった子供のイメージに結びついて。本当にこれを舞台にしていいのか、できるのか、という思いもありましたが、役者と僕の中で漂っていたイメージが繋がった、という感じでしたね。
- __
- その、役者さんたちとイメージが繋がって成立する、というところがなぜ起こるのか、可能なら深めていきたいです。
- 田中
- イメージができてから物語が成立する、と。
- __
- そうです。たとえば一人が何か本を書いても、ともすると独り合点になってしまう。それを打ち破って次の段階へ向かう、その彷徨っている段階というか。
- 田中
- なるほど・・・僕の舞台作りでは、まず「遊ぶこと」を大事にしています。シアターゲームや、演劇のワークショップでやるようなアイスブレイクから始めるんです。テキストから考えることもありますが、今回は「流れる」という要素から、みんなで歩いてみるとか。そうしていくうちに、役者が「これ面白いな」とか「この動き、楽しいかも」と感じることがあって、じゃあそれをしながらセリフを言ったらどうなるだろう、という風に作っていきます。明確なイメージに向かうというよりは、近しい要素を抜き出して遊んでみた結果、「これだったらいけるかも」というものを見つけていく感じです。
- __
- そうなんですね。
- 田中
- なので、最初のうちは役者の中でも「大丈夫かな?」「これ本当うまくいく?」という空気はありました。特に今回は物語の筋がないような作品だったので。こういう作り方は、京都で活動してらっしゃる「地点」とか、あとは「マームとジプシー」のような、役者の身体のイメージで作品を作る劇団を参考にしています。僕の今の演劇観はそこから来ている気がしますね。
- __
- つまり役者は、自分たちが発している動きがどのようなものかを体感する瞬間があると。
- 田中
- そうですね。そういう瞬間があって、たぶんお互いに「これならいける」という合意がなんとなく取れるんです。それを何回か続けて、最初の立ち上げを作るようにしています。
- __
- その合意というのは、権力に基づいたものなのか、それとも、建前上は対等な関係性の中で生まれるものなのか。
- 田中
- それで言うと、結局は僕が「面白い」というものをみんな優先して作ってくれます。もちろん共に作る意識はあるんですが。ある程度、感覚が合う役者を毎回選んでいるというのもありますし、この前に出ていただいたのも、ほぼ大学の同期の人たちなんで。もし方向性が違う提案が出た時は、まず一回そっちでやってみることもあります。でも、やってみた上で最後にやっぱりこっちにしよう、と。「これがいいからこのやり方で」と言うよりも、提案されたものは一旦受け入れて試してみる、ということはしています。だから結構遠回りなんですけど。
- __
- 一回やってみて、採用されることもあると。
- 田中
- ありますね。僕の中で、良い作品を作るのはもちろんですが、「良い稽古」にしたいな、という思いが強くあって。あまりギスギスしたくはないですし、僕が「これで、これで」と決めすぎても面白くないな、と。逆にそれがストレスになる役者さんもいるんですけど。むしろ、この役者さんはこれが苦手だとか、逆にこれが得意だから、ということを結構取り入れたりします。じゃあこれが苦手だから、こういう動きにしようとか。今いる参加者だからこそできる、みたいなのが面白いかな、という意識の方が強いです。
- __
- 分かりました、ありがとうございます。それが演劇ワークショップ型の劇作の一部なんですね。他にはどのような特徴がありますか?
- 田中
- そうですね…。稽古に入るまでの「場を作ること」を結構意識しています。例えば、最初は「最近どうだった?何かいいことあった?」みたいに話す時間を作ったり、とりあえず一旦遊んでみて、その遊びが面白かったらもうちょっと続けてみたり。すぐに稽古には入らないように、なるべくギリギリまで遊べるようにしておきたいな、と。
- __
- 時間がなかったら、なかなか難しいですよね。
- 田中
- そうなんです。今回も実際に動き出したのは2ヶ月前からくらいで、その期間で60分の作品を作るのはなかなか難しかったので、少し強引に進めた時もありました。だから、僕としてはもう少し面白いものが作れたんじゃないか、という反省もありますね。
結果的に・・・

- __
- ご自身の考え方の癖やコツが、その演劇ワークショップ型の劇作で出てしまうことはありますか。出るとすればそれはどういうところでしょうか。
- 田中
- 癖やコツ…。それで言うと、結構「イエス」を出しすぎるところがありますね。いわゆる「Yes and...」と言うと思うんですけど、演出面で動きやゲームから作る影響もあって、割と後付けしてしまう癖というか。偶然起きたことや、本人は適当にやっていたことでも、僕には面白く見えて「それで行こう」って言うと、「いやそれはダメだよ」みたいに逆に役者から止められたり少し怒られる、みたいなことがあります。僕は心から「いいじゃん」と思ってイエスを出しているんですけど、自分の中の線引きがこれでいいのかは、まだどうなのかな、という感じです。
- __
- 全体のバランスを見ないといけないと思いつつ、目の前のことに引きずられてしまう、みたいな。
- 田中
- そうですね、だから稽古で自分の思った通りに進むことがあまりないというか。もちろん「今日はこれをやろう」というプランはあるんですけど、結果的に、進んではいるものの全然思っていたのと違う何かができている、ということがあって。それが面白かったり、逆に「これはまずい」と思ったりして、次の稽古に向けてプランを練り直して、また次の稽古で違うことが起きて、という繰り返しでした。
- __
- 具体的に、今回の「君のからだは川になる」ではいかがでしたか。
- 田中
- あるシーンで、役者6人がそれぞれ海の中を漂うプランクトンみたいなイメージで、干渉したりしなかったり、というニュアンスで演出をつけようとしたんですが、それだと「ちょっと訳がわからない」という空気になってしまって。もう少し役者同士の繋がりが必要だと。そんな時別の現場のワークショップで、目をつぶってみんなで電車ごっこをする、というのがあったんです。前の人の動きに合わせて身体の感覚で空間を動いてみるというもので、「これだ」と思って稽古でやってみたら、役者からも「これならいけるかも」と言ってもらえました。僕の中ではもっとバラバラで、めちゃくちゃな、それこそお客さんを意識しないようなものになると思っていたんですけど、結果的に賑やかでワイワイした感じの作品になりましたね。
- __
- ご自身のイメージと現実が必ずしも一本化しない、と。
- 田中
- はい、それは毎回必ず起きています。結果オーライじゃないですけど、最終的に形になったらいいか、という気持ちでいます。「君のからだは川になる」も、最初はもっと静かで、詩的なイメージだったのが本当にガラリと変わったので。逆に僕が一番稽古場についていけてなかったような気がします。
- __
- おとなしく静かな詩という全体のイメージもありながら、イメージの洪水というか、ジェットコースターのようなダイナミックさもすごく感じました。ありがとうございます。
ABnormal Ceremony

- __
- 「ABnormal Ceremony」ですが、こちらは劇団アンゴラ・ステーキとの合同公演ですね。
- 田中
- はい。この中の「Drama for Airports」で、僕は演出と、役者としても出ようかなと思っています。
- __
- チラシにある「時代に逆行、流行に逆行、ナンセンス万歳」というワードがいいですね。
- 田中
- アンゴラ・ステーキのメンバーが今回掲げていることで、僕自身は、まあ、そこまででもないですけど(笑)。
- __
- 「Drama for Airports」は、アンゴラ・ステーキの中村圭吾さんの戯曲なんですね。どのような作品になりそうでしょうか。
- 田中
- ようやく形が見えてきたところです。僕は毎回、作品を作る時に「前回とは反対のことをしよう」という自分なりの意識があって。今回は前回とは逆に████した、██████████状態で舞台を作れないかな、と考えています。
- __
- ███████で?██████████ぐらいな感じですか。
- 田中
- 今のところはそうですけど、でも結局██████そうな気はしています。まだ本当に始まったばかりなので、どうなるかなという感じです。
- __
- ██も████にドラマを成立させると。会話劇ではあるんですね。
- 田中
- そうですね。中村さんの作品は不条理な会話劇なので、そのセリフの面白さがどうすれば生きるかを考えていました。それで、空港の待合室でずっと待ち続ける人たち、という場面設定をそのまま使おうと思っています。そこに色々な仕掛けを入れて作れないかな、と。
- __
- 非常に██的な██で、とても気になります。
- 田中
- 僕もまだどうしよう、というところです。さらに、稽古で役者から「これはどうだ」という案が出たんですが僕は最初「さすがにそれはノーかな」と。でもやってみたら意外といける、ということもあって。それは結構、舞台のセオリーとは反対というか、「これはしちゃダメでしょ」みたいなことを一つやっています。
- __
- それは、さらに言わない方がいいですね。
- 田中
- そうですね(笑)。僕は最初「これじゃ絶対お客さん寝るかも」と思ったんですが、それを仮置きしたら、逆に「どうやったら寝させないようにできるだろう」という話になって。僕というより役者からの挑戦を僕が受ける、みたいな変な稽古になってて、面白いですね。
- __
- 当日までの楽しみにしておきます。会場のスモールシアター KIKIは新しいスペースなんですね。
- 田中
- はい、小さなスペースです。客席は多くても25席とか、頑張れば30席くらい?今回はオープン記念ということで、ロングランでやることになりました。僕の作品の上演の他にも2作品の上演や、中村君のワークショップ、過去作の上映会などもあります。
- __
- 開会式もあるみたいですね。フェスティバルですね。
- 田中
- そうなんです。気づいたら企画が増えてて。最初は公演だけって思ってたのに、ワークショップが増え、お客さんとのお話会が増え、上映会が増え、気づいたら項目が10個ぐらいになってました。
きっかけになる
- __
- 田中さんがお芝居を始めたのはいつからなんですか?
- 田中
- お芝居自体は、幼い頃からモデル事務所に所属していて、ドラマや映画に出ることはありました。でも、演劇を本格的に始めたのは高校の演劇部からです。
- __
- 高校の演劇部からずっと続いているんですね。では高校の演劇部の時から、演出や劇作も?
- 田中
- いえ、大学までずっと俳優志望でした。でも壁に当たると言いますか、舞台は映像とやっぱり求められる演技が全然違うので。声が出ていないとか色々言われましたし。あと高校演劇は裏方と役者を兼ねることが多いので、役者をやるだけじゃない大変さもありました。演劇は好きになりましたが、自分が思っていたよりもワクワクしなかったというか、どこかモヤモヤするようになってきて。
- __
- そこから、お芝居を作る側へ入っていったということでしょうか。
- 田中
- そうですね、どちらかというと演出が好きなんですけど、そうなった明確なきっかけが大学2回生の時にあって。大阪芸大で教えてくださった石本興司さんという先生に1年間教えていただいて。その時にカルチャーショックというか、「すごい人に出会った」という感じがあって。その方が演劇と教育について話してくれた時、演劇はただ舞台の上だけではなくて、すごく色々なところに広がっている可能性を持つんだと知って、視野が広がりました。その方が演出で学内公演に参加した時「演出ってこんなに面白いんだ」と感じたんです。人と関わりたいけど上手くいかない、という思いが実はあったのですが、人と話して物語を作る演出なら面白そうだな、と。
- __
- 俳優がイメージを作り、それをお客さんに届ける手助けをする、みたいな。
- 田中
- そうですね。あとは、演出として役者自身と話して、役者の中で何か変化が起きたり、お芝居が終わった後に何か良い方向に行ったりしたらすごく嬉しいです。言葉と自分の身体を使う演劇は、人の変化にすごくダイレクトに繋がるものだな、というのがあるので。その瞬間に立ち会えるのがいいな、という意識があります。
下地についての話

- __
- 「インプロせぇへん」にも出演されていますよね。インプロ、つまり即興劇ですね。
- 田中
- はい、出ています。
- __
- 即興って、観客がすべてを受け入れる姿勢を持っているから成立するところも大きいとは思いますが、それ以上にぬまたさんの導入と采配によるところが大きいのではないかと思っています。もちろん、出演者の力量は絶対に欠かせませんが。
- 田中
- 僕もちょっと同じことを考えてました。インプロせぇへんで一番大事なのは、実は最初のぬまたさんの前説だと思っていて。あれを聞かずに、かつ初めてインプロを見るのと、「これはアドリブで、こういうルールです」と最初に聞くのとでは、たぶん180度ぐらい違うな、と。
- __
- 即興は何かを知っている観客と、そのルールの説明を改めて実施することで、場の下地が出来る。インフラ整備とすら言っていいかもしれない。
- 田中
- 僕の作品でも、そういう意識があります。最初に「こういうルールですよ」「こういう形で進みますよ」というのを見せるのと見せないのでは、お客さんの共感が全然違うなと思って。例えば「君のからだは川になる」の冒頭の電車ごっこも、実は鬼ごっこになっていて、タッチされたら鬼が代わるというルールで動いていたんです。そういう「今からこういうことしますよ」というのを、できれば入れたいな、と。その意識は「インプロせぇへん」で改めて思ったことですね。
- __
- なるほど。ただ・・・演劇はどうしても、もともと興味がある人しか観に来ないというハードルがありますよね。なので、インフラがどうのとか導入がどうのとか言ってる場合じゃないかもしれない。突然こんなことを申し上げて申し訳ないのですが、そういう現実はつきまといますね。
- 田中
- それはいつも思います。演劇を観に来る人、例えば大阪芸大の舞台に来る人は、間違いなく舞台に興味がある人しかいないというか。他の音楽や美術だと、あまり知らずにふらっと来る人も割と多い印象があるんですけど。
- __
- ライブハウスやクラブとかのようにはね。
- 田中
- でも、最近はそのハードルを越えようっていう人がいるなと感じていて。それこそ東京の南極(元南極ゴジラ)のインタビューがヤングジャンプに掲載されたり、ダウ90000がお笑いと演劇の垣根を壊そうとしていたり。僕の実感では、今、徐々に演劇とほかの領域が繋がって浸透してきている感じがします。
質問 内藤彰子さんから田中陽太さんへ
- __
- 前回インタビューさせていただいた、 喜劇結社バキュン!ズと第九惑星の内藤彰子さんから質問です。「脚本書きなどの作業がはかどる場所とかってありますか?」
- 田中
- 無難にカフェとか、ファミレスとかですね。サイゼリヤとかで書いたりします。家みたいな場所だとダレてしまうというか。
- __
- 騒がしい方がいいですか、それとも静かな方がいいですか。
- 田中
- どちらかと言えば静かなんですけど、図書館みたいに静かすぎると逆に落ち着かなくて。だからファミレスでも、人が少ない時間帯とか、人気がなさそうなところに行ったりします。
- __
- 自分の部屋じゃない、というのが大事なんですかね。
- 田中
- そうですね。僕、結構環境に左右されやすいんで、自分の部屋だとすごい内省的というか、自分の個人的なことを書きがちだなって最近気づいて。逆に、勢いのある文章を書きたい時は、梅田みたいな人の多い場所の方が書けるな、という気づきが最近ありました。
- __
- 土地の力が干渉してくるのかもしれないですね。
- 田中
- あると思います。
展開していく、広がっていく

- __
- 今回のインタビューはそろそろ終わりですが、他に何かお話になっておきたかったこととかありますでしょうか。
- 田中
- 一個だけあって僕、元々あんまり演劇好きじゃなかったという話なんです。
- __
- なるほど。
- 田中
- お芝居をすること自体は好きだったんですけど、演劇部に入った時同年代の高校生は舞台でもダンスとかライブとかにばかり注目していて、演劇には見向きもしてくれない。演劇の面白さを大人や先輩に聞いても、たとえば「会話で物語が立ち上がるところ」と教えてはくれるんですけど、それなら映画でもいいんじゃないかと思ってしまって。自分の中で演劇のセールスポイントが見つからなかったんです。面白いけど誰にも見てもらえないメディアなんだな、という諦めの気持ちがあの頃ありました。その肩身の狭い時期があった上で、大学に入って先ほどの石本先生に「演劇は舞台だけじゃない」と聞いて、自分の中の芯を取り戻したというか。だから今はすごく楽しくやれていますが、その前は全然楽しくなかったな、というのを思い出して。これは自分の中では結構大きなことだったな、と言いたかったです。
- __
- ありがとうございます。演劇という技術にこだわっているというよりは、展開していく、広がっていく、という行動を大切にされているのかもしれませんね。その点は私個人も同じですが。
- 田中
- そうですね。演劇を単純に演劇と捉えるんではなくて、社会とか音楽とかスポーツとか、他のものに置き換えてみようという意識が結構あって。純粋に演劇をやろうというよりも、もっと漠然とした何かを作ろう、という意識でいます。この前の公演で最初にミュージカルみたいなのを入れたのも、もっと音楽や踊りとか、他の要素と繋げたいという意識があったのかもしれない、と今思いました。
- __
- 我々は、演劇というメディアにたまたま位置しているだけかもしれないですね。
レーザーポインター
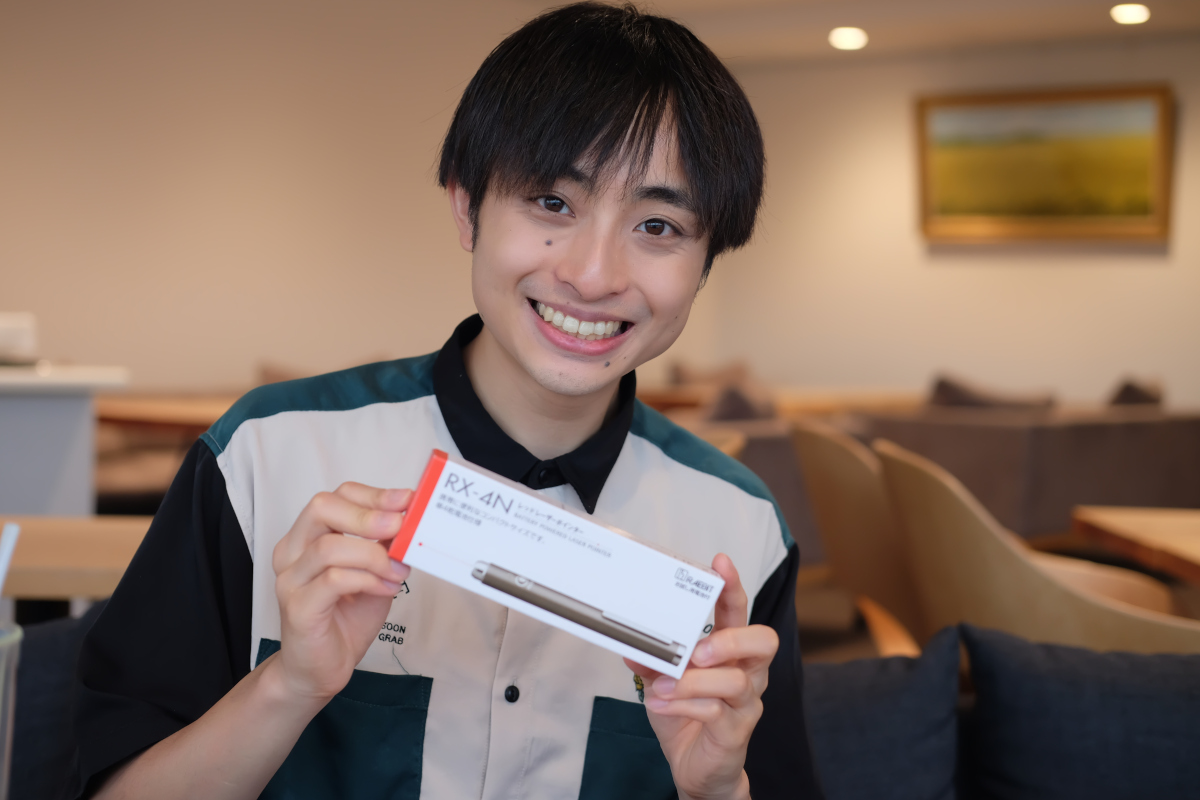
- __
- 今日はですね、お話を伺えたお礼にプレゼントを持ってまいりました。
- 田中
- ありがとうございます。(開ける)レーザーポインターですか。
- __
- 最初に申し上げておくと、それはプレゼンの時にしか使えないと思います。人の目に入ると危ないので。
- 田中
- なんかお洒落ですね。もう今これを次の公演に使えないかなとか考えてました。ありがとうございます。
- __
- プレゼン演劇をする時には使えるかもしれないですね。










